目次
はじめに
保育園における「食物アレルギー対応マニュアル」。
園の安全を守る大切なツールですが、実際は…
- 形式的に存在するだけで使われていない
- 職員が“見たことない”まま現場で対応している
- 情報が古く、今の体制に合っていない
ということも珍しくありません。
 見てみよう!
見てみよう!今回は、園で“本当に使える”アレルギー対応マニュアルにするための見直しポイントを、保健・看護の視点からお伝えします。
まずチェックしたい「ありがちなマニュアルの課題」
1. 更新日が2年以上前のまま
→ 実際の対応体制と合っていない(職員・担当・医療連携先など)
2. 医師監修がなく、根拠が不明
→ 説明責任を問われたとき、信頼性に欠けるリスクあり
3. 実務に合っていない(理想論で終わっている)
→「発作時は医療機関に連絡」だけで、園内対応が不明確
📝本音メモ
「もし今この子がアレルギー反応を起こしたら…」
そう想像したとき、“このマニュアル、実際どう動く?”がすべてのチェック基準になります。
マニュアル見直しのポイント5つ


① 対象者リストを最新化(クラス別・食品別)
- 担任だけでなく、全職員が即時確認できる形式にする
- 実名+顔写真入りリスト(給食室・職員室にも掲示)
② 提供メニューの情報共有フローを明確に
- 調理室→担任→看護師の流れを図で示す
- 献立変更時や代替食の伝達ルールを統一する
③ エピペン対応フローの見直し
- 使用判断 → 保護者・園長・救急対応の流れを明文化
- 「誰が打つか」を曖昧にしない(看護師以外の対応も記載)
④ 嘔吐・蕁麻疹・咳などの軽微症状の初動判断フロー
- 「様子を見る」だけでなく、“見る基準”を言語化する
- 担任でも判断しやすいよう、“色・範囲・呼吸状態”など具体的に記載
⑤ 保護者・園医との定期的な見直し確認
- 年1回の更新タイミングを設定(例:3月末 or 4月初旬)
- 園医のサイン・保護者との同意確認も忘れずに
実用フォーマット例(導入・配布資料に)
- ✦ 食物アレルギー個別管理表(食材別アレルゲン一覧+症状+対応)
- ✦ エピペンマニュアル(写真入り・吹き出し付き1枚ペーパー)
- ✦ 職員向け「アレルギー事故の初動対応フロー図」
- ✦ 保護者向け確認用チェックリスト(“お願いしたいこと”一覧)
📝本音メモ
実際に事故が起きた園の報告書を見ると、**「情報共有ミス」「対応のばらつき」**がほとんどなんです。
まとめ|マニュアルは“管理職”だけのものじゃない
食物アレルギー対応マニュアルは、
保育士も、調理員も、看護師も、すぐに使える「園の安全装置」。
紙で配るだけで終わらせず、
- 職員が読んでるか?
- 対応が統一されてるか?
- 現場で迷わず動けるか?
この3つを意識して見直すことで、“生きたマニュアル”になります。

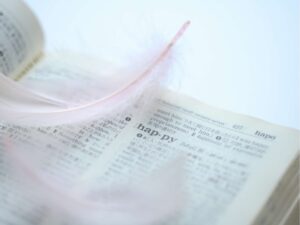









コメント