目次
はじめに
保育園で働いていると、感染症が流行するたびに
「職員向けに研修や話をしてもらえませんか?」と頼まれることがあります。
でも…
- 何をどこまで話せばいい?
- 資料ってどう作るの?
- 保育士さんたちが退屈しないようにするには?
今回は、**「保育士向け感染症研修の作り方」**を、現場目線と実体験でまとめました。
はじめて担当する方も、ぜひ参考にしてみてください!
研修の目的は「情報共有」より「実践につながること」

研修の目的は「知識の詰め込み」ではありません。
- 保育士が“明日からできる”ことを共有する
- 現場の対応を「統一」する
- 不安を減らし、自信を持って対応できるようにする
📝本音メモ
知識を教えるより、“実際にどう動くか”を整理する時間にすると、
研修後の反応がぜんぜん違ってきました。
研修構成の基本フロー(30~45分の場合)
1. はじめに(5分)
- 「こんな場面、困っていませんか?」という導入
- 感染症対応における園の現状や課題を共有
2. 感染症の基礎知識(10分)
- 流行しやすい感染症の特徴(例:RS、インフル、ノロ、アデノ)
- 登園の目安・隔離の基準・家族の感染時の対応
📝保育士が気になるのはここ👇
- 「いつまで休ませたらいいの?」
- 「どんな症状のとき、クラスに報告するの?」
3. 園内での対応の統一(10〜15分)
- 嘔吐時の対応・消毒方法・汚物処理の流れ
- 感染者が出たときのクラス内の対応ルール
- 職員同士で確認すべきこと、引継ぎのしかた
📄チェックリスト形式で共有すると効果的!
4. ロールプレイ・クイズ・事例共有(5〜10分)
- クイズ:「この対応、OK? NG?」
- 事例紹介:「以前こんなことがありましたが…」
→ 保育士の参加型にすると、記憶にも残りやすい!
5. まとめと質疑応答(5分)
- 明日から実践することをリスト化
- 保護者対応で不安なことも、ここで相談を受けやすい
スライド・資料づくりのコツ

✔ 文字を減らす!画像・イラストで視覚的に
- 病原体のイラスト
- 嘔吐処理の手順フロー図
- 注意マークやチェックボックスで強調
✔ 「保育士目線」の言葉で書く
- ✕「ノロウイルスはRNAウイルスで…」
- 〇「感染力が強く、少量でもうつります。1人出たら、クラス内は全員が“感染しているかもしれない”つもりで」
✔ 園内オリジナル資料が◎(配布物におすすめ)
- 園で決めた消毒液の希釈表
- 嘔吐物処理の手順+図
- 「困ったときの相談フロー(園長/看護師/主任)」など
よくある質問&工夫したポイント
💬 Q:「先生たちが静かに聞いてくれません…」
→ 序盤で「あるあるネタ」や笑える話を入れると空気がゆるみます。
💬 Q:「質問が出ないときはどうする?」
→ 事前に1つ2つ“よくある質問”を用意して、先に話してみると◎
まとめ|“伝わる研修”は「対話」でつくるもの
感染症研修で大事なのは、
「知ってもらうこと」ではなく、「一緒に考えてもらうこと」。
- 現場の悩みを共有する
- 対応を統一し、安心してもらう
- そして、“看護師がいてくれてよかった”と思ってもらえる時間にすること
看護師としての専門性を、現場にやさしく落とし込んでいきましょう。



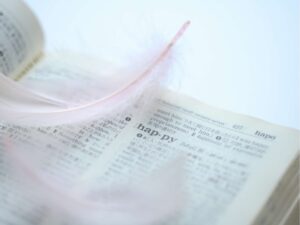







コメント